まずはじめにお断りしておかなければならないことは、ナイハンチ運動法は、古い沖縄の空手の型をもとにしていますが、各闘技の練習ではないということです。運動法の説明では、何故このような動作をするかの説明には、戦いのための身体操法も混ぜて説明しますが、目的としては、体幹の操作法を学び、体幹の動的安定性を身につけるために、一人で行う運動法です。したがって、基本的にナイハンチ運動法は、力を入れず、ゆっくりと行います。ゆっくりの動きの中で、体幹の操作法を自得していくのです。
次に、動的な体幹の安定について説明します。
歩行に、動的歩行と静的歩行があるということをご存知の方もおられるかもしれません。静的歩行とは、片方の足に完全に体重を乗せてから、他方の足を動かして、次にその足に体重を完全に移してから、先に体重を乗せていた足を浮かして、前に進めるといった歩行法です。初期の頃の二足歩行ロボットの歩行が静的歩行で、見たことのある方も少なくないと思いますが、人間の普通の歩行に比べて不自然に感じたのではないでしょうか。静的歩行では、早く歩くことは困難です。
人間の通常の歩行は動的歩行と言って、身体の重心を前によろめくようにして、左右の足を交互に前に出して、安定を図るのです。この歩行は、静的歩行に比べて、重心が左右にあまりぶれずに、早く歩けるのが特徴です。
動的な体幹の安定とは、よろめきながらも転ばずに、よろめきながらも比較的自由に動きを変化させることができることです。これは、今までの身体の安定法とは、概念が違います。両足をしっかり踏みしめて、重心を身体の中に置く安定は、動くには不便です。重心を身体の外に置くと、よろめいて転びそうになる。それを体幹部の操作で安定させて、転ばずに動き回れるようにするのが、動的な体幹の安定です。
古い空手の型が、何故体幹の動的安定を得させるように作られたのでしょうか。空手の攻撃は主に突きや蹴りです。その突きや蹴りが威力のあるようにするには、重心を身体の外に出して、突きや蹴りに体重を乗せなければなりません。しかし、普通の人が突きや蹴りに体重を乗せると、かわされた時によろめいて転んでしまいます。そこで、体重を乗せて、言い換えればよろめいても転ばないように動的に体幹を安定させなければならなかったのだと思うのです。
これは、余談ですが、動的に体幹を安定させるナイハンチ運動法は、高齢者の転倒予防にも活かせるのではないでしょうか。身体を静的に安定させるだけでは、歩行の時の転倒予防になりません。歩いても、よろめいても転ばないように、体幹の動的安定を図ることが重要なのではないでしょうか。
実際、私は60歳の時に、過労からと思われるめまい・吐き気で入院しましたが、1週間足らずでまだふらつくままで退院しました。帰宅直後に、ナイハンチ初段の型を行ってみると、確かに入院前よりよろめくのですが、転倒はしませんでした。
最後に、何故このブログで、ナイハンチ運動の体幹の身体操作を説明をするかと言うと、独習には目指す身体操作の理解が必要だからです。
講道館柔道の創始者の嘉納治五郎は、それまでの柔術が、稽古の中で自然にコツを会得するのに対して、講道館柔道では先に原理を説明してから、実際に練習した方が習得が早いと考えたようです。
一人稽古、独習を行なうにも、どのような身体操作を目指すかを知っておくと、効果を得やすいと思うからです。
それでは次回より、具体的にナイハンチ運動法を、その身体操作法も含めて説明していきます。ゆっくりと力を入れずに、何回も行っていけば、身体の操作法が体感できるようになってくるでしょう。


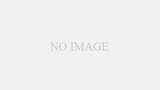
コメント